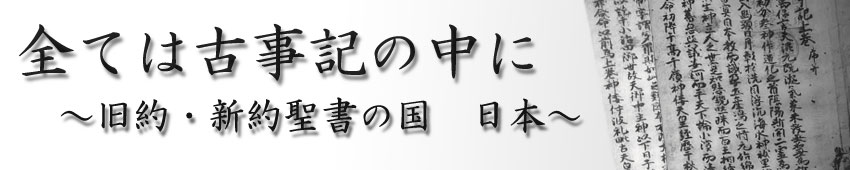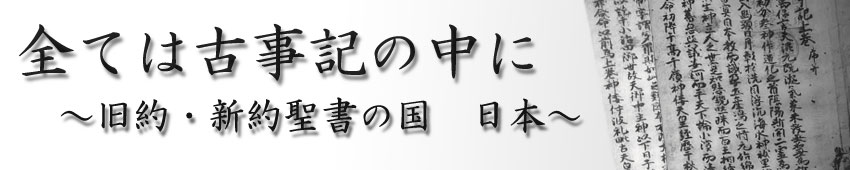| 5-(9).大神神社、墨坂神社、大坂山口神社の配置 |
古事記の崇神天皇の条には、以下の話が記載されています。
(崇神天皇の御世に疫病が大流行し、多くの民が亡くなります。そして、崇神天皇が神意を問う為に床に入ると、夢に大物主大神が現われて、意富多々泥古という人に自分を祀らせるならば疫病はおさまると告げられます。そこで、意富多々泥古を探させるために人を遣わすと河内国の美努村で見つかります。)
すると天皇はたいそう喜んで、「これで天下は穏やかになり、国民は栄えるだろう」と仰せられた。
そして、ただちに意富多々泥古を神主として、御諸山に意富美和之大神を斎き祀られた。
また、伊迦賀色許男命に命じて、天の八十びらか(※祭りに用いる多くの平たい土器)を作って、天つ神の社、地つ祇の社を定めてお祀りになった。
また、宇陀の墨坂神に赤色の楯と矛を献り、また、大坂神に黒色の楯と矛を献り、また、坂の上の神や河の瀬の神に至るまで、ことごとく漏れ残すことなく弊帛を献ってお祀りになった。
これによって疫病がすっかりやんで、国内は平穏になった。
|
ここでは、以下の3つの神社が祀られたことになっています。
| 神 名 |
詳 細 |
御諸山
意富美和之大神 |
御諸山は奈良県桜井市の三輪山のこと。
大神神社では、三輪山自体が神体とされる為、拝殿のみで本殿はない。主祭神は大物主大神で、日本国内で最も古い神社のうちの1つであると言われている。 |
| 宇陀の墨坂神 |
奈良県宇陀郡にある墨坂神社。祭神は、天御中主神、高皇産霊神、神皇産霊神、伊邪那岐神、伊邪那美神、大物主神の六柱で、まとめて墨坂大神と呼ばれる。
日本書紀の神武紀には兄磯城が炭に火をつけて天皇軍を阻んだとの故事がある。
|
| 大坂神 |
大坂山口神社のことであるが、同神社は 奈良県北香芝市に逢坂と穴虫の2ヵ所にあり、古事記に記載されたのがどちらなのかは諸説あってはっきりしない。
逢坂の方の祭神は、大山祇命、須佐之男命、神大市比売命。穴虫の方は、大山祇命、須佐之男命、天児屋根命。
|
この3つの神社の配置を調べてみると、次の図の通りです。

大坂山口神社(穴虫)と三輪山と墨坂神社が一直線に並んでいることが分かります。
具体的な方位角(注)は94度です。
(注)方位角・・・北を0度とした時の角度。東は90度、南は180度になる
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
| 大坂山口神社(穴虫) |
三輪山 |
94°04′12.70″ |
16,720.170(m) |
| 三輪山 |
墨坂神社 |
94°41′15.69″ |
8,623.520(m) |
※緯度経度の算出は、「MAPPLE 地図」を使用
※方位角と距離は、「測量計算(距離と方位角の計算)」のPGMを使用
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
| 大坂山口神社(穴虫) |
北緯34度32分32秒 |
東経135度41分18秒 |
|
| 三輪山 |
北緯34度31分53秒 |
東経135度52分12秒 |
|
| 墨坂神社 |
北緯34度31分30秒 |
東経135度57分49秒 |
|
そして、大坂山口神社(穴虫)から94度の方角にあるのが、伊勢の月読宮です。
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
| 大坂山口神社(穴虫) |
月読宮 |
94°29′03.17″ |
96,146.664(m) |
| 大坂山口神社(穴虫) |
内宮(皇大神宮) |
95°42′26.40″ |
96,068.779(m) |
※内宮の方は参考まで。
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
| 月読宮 |
北緯34度28分12秒 |
東経136度43分54秒 |
|
| 内宮(皇大神宮) |
北緯34度27分6秒 |
東経136度43分43秒 |
|
つまり、この3つの配置で、「5-(8).住吉大社の配置」で示した住吉大社の配置と同じく、日本列島を縦断する十字架の交点に位置する月読宮(※)を暗示・示唆していると言えます。
※「5-(7)伊勢神宮の配置の秘密(グランドクロス)」を参照
なお、5−(7)で示した仮説、「3つの神社を1セットとする時は、『一直線に並ぶのは不可で、二番目の神社は起点となる神社から見て、3度ずれなければならない』というルール」はここでも当てはまりません。
ただし、これらの神社の祭神を見ると、大物主神や須佐之男命で国津神系であり、「3度ずらすというルール」は天津神系のみで、国津神系に適用する必要はないのかも知れません。
ちなみに、上記、方位角94度のラインから外れている逢坂の方の大坂山口神社ですが、こちらは、穴虫の方と66度のライン上に配置されています。
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
大坂山口神社
(穴虫) |
大坂山口神社
(逢坂) |
66°16′29.12″ |
612.731(m) |
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
大坂山口神社
(逢坂) |
北緯34度32分40秒 |
東経135度41分40秒 |
|
方位角66度は夏至の日に太陽が昇る方角(※)であり、こちらも意図的に配置されていることが分かります。
(※)夏至の日に太陽が昇るのは、真東から約23.4度、北の地点。方位角は90度-23.4度で66.6度となる
---------------------- 以下、2010.5.19追加 --------------------------
≪訂正≫
夏至の日に方位角66度の方向から太陽が昇るのは赤道付近の場合であり、緯度によって、その方位角は異なります。
大坂山口神社(逢坂)の緯度で、夏至の日に太陽が昇るのは方位角60度の方向となります。(※「日月出没計算サービス」のPGMを使用。計算年月は2010年6月21日で計算)
なお、上記ラインが方位角66度となっているのは、地軸の傾き(23.4度)を意識しているのではないかと思われます。
---------------------- 以上、2010.5.19追加 --------------------------
住吉大社と合わせて、まだ2例だけなので単なる仮説に過ぎませんが、「グランドクロスのパワーを日本全国に行き渡らせる為の霊的結界」と言ったような発想があるのかも知れません。
|
|
|