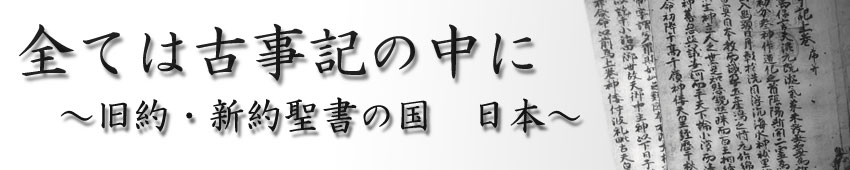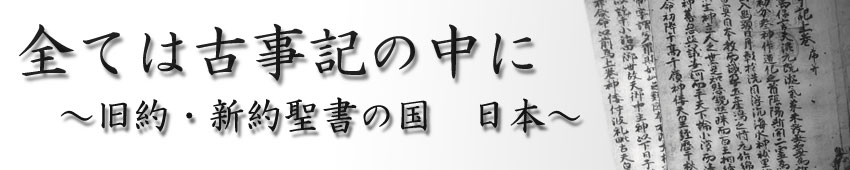| 5-(61).鏡餅と三種の神器と蛇(その2) |
※当記事は(その1)からの続きです。
3.鏡餅と三種の神器
これまでは、鏡餅の餅に絞って見て来ましたが、鏡餅と言えば、以下のようなものがオーソドックスな形でしょう。
2段の鏡餅の上に、串柿と橙です。なお、地方によっては、鏡餅が3段であったりするところもあるようです。
メインである餅については、その意味するところを(その1)で見ましたので、それ以外の橙と串柿がどのような意味を持っているのか、一般的な説明を見てみましょう。
『日本の「行事」と「食」のしきたり』 P.22-23(抜粋) (新谷尚紀/青春出版社/2004)
○橙・・・実が熟してからも長く木から落ちずに育つことから、家が「代々」にわたって長寿であるようにとの願いをこめたもの。
○串柿・・・家族の円満につながる縁起物 |
橙は、「代々」との語呂合わせで、長寿の願いを込めたものであり、また、串柿の方は、詳しいことは明記されていませんが、複数の柿が一つにつながっている形状が家族円満を表しているということではないかと思われます。
さて、この鏡餅ですが、Wikipedia「鏡餅」によると以下の通り、橙、串柿、鏡餅が「三種の神器」を表してもいるようです。
○橙 ・・・ 八尺瓊勾玉
○串柿 ・・・ 草薙剣
○鏡餅 ・・・ 八咫鏡 |
ただし、鏡餅が八咫鏡を表しているのなら、上図のように2つ存在することになり、中途半端な気がします。「三種の神器」としての八咫鏡は、あくまで一つのはずです。
そして、この謎を解く鍵であると思えるのが、日本ではなく、ユダヤの「三種の神器」です。
日本の「三種の神器」が、ユダヤの「三種の神器」を象徴しているという説を飛鳥昭雄氏が唱えています。
ユダヤの「三種の神器」とは、契約の箱に入れられていたと言う、十戒の石板、マナの壺、アロンの杖のことで、新約聖書の『ヘブライ人への手紙』には次のように記載されています。
『ヘブライ人への手紙』 9章1-5節 (新共同訳・日本聖書協会)
さて、最初の契約にも、礼拝の規定と地上の聖所とがありました。すなわち、第一の幕屋が設けられ、その中には燭台、机、そして供え物のパンが置かれていました。この幕屋が聖所と呼ばれるものです。また、第二の垂れ幕の後ろには至聖所と呼ばれる幕屋がありました。そこには金の香壇と、すっかり金で覆われた契約の箱とがあって、この中には、マンナの入っている金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の石板があり、また、箱の上では、栄光の姿のケルビムが償いの座を覆っていました。こういうことについては、今はいちいち語ることはできません。
(注)「マンナ」は「マナ」に同じ。 |
十戒の石板とは、モーセが神から与えられた十戒を刻んだとされる石板。アロンの杖とは、モーセが神から授けられたもので、モーセとアロンが使用していた奇跡を起こすことのできる杖のこと。また、マナの壺とは、モーセに率いられたイスラエルの民が飢えた際、神が天から降らせた食べ物であるマナを入れた壺のことです。
このユダヤの「三種の神器」と日本の「三種の神器」の対応は、飛鳥昭雄氏によれば次の通りです。
○八尺瓊勾玉 ・・・ マナの壺
○草薙剣 ・・・ アロンの杖
○八咫鏡 ・・・ 十戒の石板
※『失われたキリストの聖十字架 「心御柱」の謎』 P.373-384 (飛鳥昭雄・三上たける/学研/2002) |
この説を前提として、再度、上記の鏡餅のイラストを見てみましょう。むしろ、鏡餅は、日本のよりもユダヤの「三種の神器」の方に近いことが分かります。
まず、マナの壺は、『ヘブライ人への手紙』にある通り、「金の壺」とされるので、橙の色はマナの壺に近いですし、また、橙の形状も、勾玉のような曲がった形よりは壺の方がより近いと言えるでしょう(壺の形状にもよりますが)。
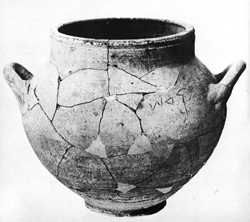
ベエルシェバから発掘された素焼きの壺。ヘブライ語で「聖」と書かれている。 |
次に、串柿の色は、草薙の剣が銅剣であったとしたら、どちらにより似ているとは言えないかも知れません。ただし、アロンの杖は、至聖所に置かれていた際、アーモンドの実をならせたという話が旧約聖書に記載されていますが(民数記17章23節)、串柿の方にも実がついています。
最後に、餅ですが、形状ではその名の「鏡餅」の通り八咫鏡に近いですが、個数に着目すれば、十戒の石板は2つの石板に5つずつ戒が掘られていたので2枚あり、やはり、十戒の石板の方と一致しています。
また、色では、十戒の石板の色が不明なので何とも言えないところですが、大理石のようなものであれば、白に近い色であった可能性もあります。
以上、総じて鏡餅を見れば、日本のよりも、ユダヤの「三種の神器」の方により相似しているのです。
※(その3)へ続く
◆参考文献等
| 書 名 等 |
著 者 |
出 版 社 |
『日本の「行事」と「食」のしきたり』
|
新谷尚紀 |
青春出版社 |
『失われたキリストの聖十字架 「心御柱」の謎』
|
飛鳥昭雄・三上たける |
学研 |
|
|
|