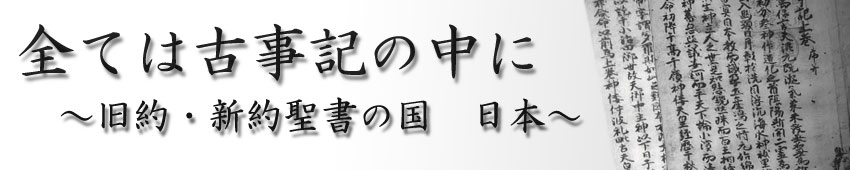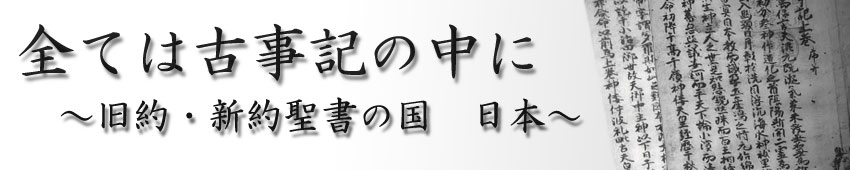| 5-(30).熊野三山の配置 |

熊野三山とは、和歌山県にある三つの神社、熊野本宮大社、熊野速玉大社、熊野那智大社の総称です。
三社とも右図のような三本足のカラスである八咫烏をマークとして使用しており、八咫烏と非常に関係が深い神社です。
また、「伊勢に七度、熊野に三度」という言葉があるように、中世から近世にかけて、伊勢詣と並んで熊野詣は庶民の念願の一つであり、人々の信仰を大いに集めた神社でした。
なお、その参詣道は2004年7月に「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産に登録されました。現在、道が世界遺産に登録された例は熊野とサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼路の2例だけです。
これら三社の祭神は次の通りです。
<熊野本宮大社> 創建:不明(祟神天皇65年という伝承がある)
| 社 殿 |
祭 神 |
| 上四社 |
|
第一殿(西御前) |
熊野牟須美大神(伊邪那美大神)・事解男神 |
| 第二殿(中御前) |
速玉之男神・伊邪那芸大神 |
| 第三殿(證証殿) |
家津美御子大神(別名:熊野座大神、熊野加武呂乃命) ※主祭神
|
| 第四殿(若宮) |
天照皇大神 |
| 中四社 |
|
第五殿(禅児宮) |
忍穂耳命 |
| 第六殿(聖宮) |
瓊々杵命 |
| 第七殿(児宮) |
彦穂穂出見命 |
| 第八殿(子守宮) |
鵜葺草葺不合命 |
| 下四社 |
|
第九殿(一万十万) |
軻遇突智命 |
| 第十殿(米持金剛) |
埴山姫命 |
| 第十一殿(飛行夜叉) |
弥都波能売命 |
| 第十二殿(勧請十五所) |
稚産霊命 |
<熊野速玉大社> 創建:不明(景行天皇58年という伝承がある)
| 社 殿 |
祭 神 |
| 上四社 |
|
第一殿(結宮) |
熊野夫須美大神・伊奘冉尊 |
| 第二殿(速玉宮) |
熊野速玉大神(※主祭神)・伊奘諾尊 |
| 第三殿(證証殿) |
家津御美子大神・国常立尊 |
| 第四殿(若宮) |
天照皇大神 |
| (神倉宮) |
高倉下命 |
| 中四社 |
|
第五殿(禅児宮) |
天忍穂耳尊 |
| 第六殿(聖宮) |
瓊々杵尊 |
| 第七殿(児宮) |
彦火火出見尊 |
| 第八殿(子守宮) |
鵜葺草葺不合尊 |
| 下四社 |
|
第九殿(一万宮) |
国狭槌尊 |
| 第九殿(十万宮) |
豊斟渟尊 |
| 第十殿(勧請宮) |
泥土煮尊 |
| 第十一殿(飛行宮) |
大斗之道尊 |
| 第十二殿(米持宮) |
面足尊 |
<熊野那智大社> 創建:不明(仁徳天皇5年という伝承がある)
| 社 殿 |
祭 神 |
| 第一殿(瀧宮) |
大巳貴神 |
| 第二殿(證証宮) |
家津御子神 |
| 第三殿(中御前) |
速玉神 |
| 第四殿(西御前) |
夫須美神 ※主祭神 |
| 第五殿(若宮) |
天照大神 |
| 第六殿(八社殿) |
|
禅児宮 |
忍穂耳尊 |
| 聖宮 |
瓊々杵尊 |
| 児宮 |
彦火火出見尊 |
| 子守宮 |
鵜葺草葺不合尊 |
| 一万宮・十万宮 |
国狭槌尊・豊斟渟尊 |
| 米持金剛 |
泥土煮尊 |
| 飛行夜叉 |
大戸道尊 |
| 勧請十五所 |
面足尊 |
※耳慣れない祭神も多いですが、その点については別途、機会をあらためて解説したいと思います。
この三社の配置を調べてみると、次の通りになります。
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
熊野本宮大社
(旧社地) |
熊野速玉大社 |
120°04′40.46″ |
22,460.961(m) |
熊野本宮大社
(旧社地) |
熊野那智大社 |
149°27′31.52″ |
21,242.450(m) |
| 熊野那智大社 |
熊野速玉大社 |
50°54′13.18″ |
11,145.503(m) |
※緯度経度の算出は、「MAPPLE 地図」を使用
※方位角・・・北を0度とした時の角度。東は90度、南は180度になる
※方位角と距離は、「測量計算(距離と方位角の計算)」のPGMを使用
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
熊野本宮大社
(旧社地) |
北緯33度49分50秒 |
東経135度46分36秒 |
現在の社殿は1889年の大水害によって移転したものなので、旧社地の座標を使用 |
| 熊野速玉大社 |
北緯33度43分44秒 |
東経135度59分11秒 |
|
| 熊野那智大社 |
北緯33度39分56秒 |
東経135度53分35秒 |
|
まず、熊野本宮大社を起点とした他の2社への方位角が120度と150度になっています。(※「熊野本宮大社→熊野那智大社」のラインは方位角149度27分ですが、誤差の範囲内であると思われます)
つまり、この三社で30度(150度−120度)の角度を形成しており、また、方位角が120度と150度ですから、その角度は東西、もしくは南北のラインを基準にしていることが分かります。
また、30度は360度を12等分した角度で、この角度が示唆するものは「12」です。
この「12」という数字は、熊野三山がこだわって使用している数字であり、先に上げた社殿に割り振られた数字も「12」もしくは「6」(12の約数)までとなっています。
熊野速玉大社では、神倉宮には数字は割り振られていませんし、第九殿が二つあったりしています。また、熊野那智大社では、第六殿として残りの社殿をまとめてしまって、6までしか割り振っていません。「12」という数字への深いこだわりを表していると言えるでしょう。
また、熊野速玉大社例大祭で行われる神馬渡御式では、馬に乗せられた人形の背には、萱穂12本に牛王宝印12枚を挟んだものが差され、さらに、熊野那智大社例大祭の扇会式では礼殿前に12本の扇御輿が並べられます。
次に、「熊野那智大社→熊野速玉大社」のラインは方位角が50度になっています。
これは、北を0度とした時の角度ですので、東を基準にすると40度(※90度-50度)になります。
この40度は360度を9等分した角度であり、この「9」という数字も熊野三山では好んで使用している数字です。
熊野古道沿いにある神社群を総称して「熊野九十九王子」と呼びますし(※実際には99社もない)、熊野速玉大社例大祭で行われる早船競漕では、9艘の船に9人の漕ぎ手が乗って競争します(※他に、船頭が1人、神職1人の計11人が乗船)。
次に、「熊野本宮大社→熊野速玉大社」の方位角120度のラインを北西に延長すると島根の出雲大社にたどり着きます。
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
| 出雲大社 |
熊野本宮大社
(旧社地) |
120°40′24.07″ |
332,403.530(m) |
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
| 出雲大社 |
北緯35度23分56秒 |
東経132度41分17秒 |
|
熊野三山で祀られている家津美御子大神(家津御美子大神・家津御子神)は須佐之男命のことだとされており、そして、出雲大社では明治になるまで須佐之男命が主祭神として祀られていました。
また、出雲と紀州は古代に深い関わりがあったと考えられており、例えば、出雲には熊野大社があり、和歌山の熊野三山とどちらが源流になったのか諸説が分かれていますし、また、古事記では大国主命が兄弟たちの難を逃れて、一旦、紀州へ身を寄せています。
最後に、熊野本宮大社の真北には京都の下鴨神社があります。
| 出発点 |
到達点 |
方位角 |
距離 |
| 下鴨神社 |
熊野本宮大社
(旧社地) |
179°58′00.99″ |
133,701.787(m) |
<参考:各神社の緯度経度>
| 神社名 |
北緯 |
東経 |
備考 |
| 下鴨神社 |
北緯35度2分9秒 |
東経135度46分33秒 |
|
下鴨神社の祭神は賀茂建角身命と玉依媛命であり、他の記事で述べた通り、その正体は須佐之男命と天照の一人目の巫女の夫婦です。
また、下鴨神社と共に加茂神社と総称される上加茂神社の祭神は、その夫婦の子の賀茂別雷神であり、この人物は「5-(29).八咫烏=聖霊」に記載した通り、八咫烏でもありますから、やはり熊野三山との深い関連性が伺えます。
以上の内容を地図上に示すと次の通りとなります。
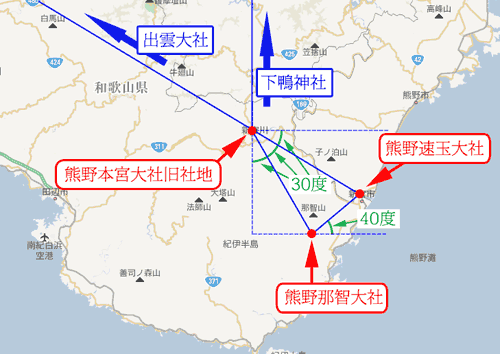
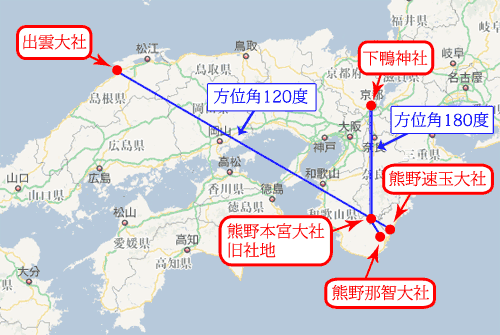
熊野三社の祭神には耳慣れない名前の神もおり、また、熊野には徐福渡来伝説があって、熊野速玉大社の近くには徐福が目指したと言われる蓬莱山という名の山があったりもします。
熊野三社には、まだまだ多くの謎が隠されていそうです。
|
|
|