|
※当記事は記事「七福神と『ヨハネの黙示録』(その1)」からの続きです。
(その1)でも記載したように、当記事では、「他の七福神もキリスト教、特に『ヨハネの黙示録』に関連しているのではないか」という観点で考察をして行きたいと思います。
まず、最初に、七福神について説明しておきましょう。
七福神は、ご存知の通り、七柱の福の神の集団であり、室町時代末期に京の町衆文化の中で成立しました。
ただし、七福神の成立前から、鞍馬の毘沙門天、比叡山の三面大黒天(※(その1)で記載した三面六臂の大黒天)、西宮の恵比須、竹生島の弁才天が既に篤い信仰を集めており、特に、恵比須と大黒天は一対の福神として祀られ、しばしば絵にも描かれていました。
こうして、当時、上方で流行していた恵比須・大国天の二神を軸に、弁才天、毘沙門天が加わり、一時、吉祥天、天宇受売命、宇賀神、虚空蔵、猩々などが加えられることもありましたが、現在は、以下の七柱となっています。
|
神名 |
福徳 |
| ① |
恵比須 |
漁労、労働、商売の神 |
| ② |
大黒天 |
五穀豊穣、財福、飲食の神 |
| ③ |
弁才天(弁財天) |
音楽、知恵、弁説、財福の神 |
| ④ |
毘沙門天 |
仏法守護、北方守護の神 |
| ⑤ |
福禄寿 |
幸運、長寿の神 |
| ⑥ |
寿老人 |
長寿、健康の神 |
| ⑦ |
布袋 |
吉凶の占い、福徳の神 |
なお、七福神の原形の一つとして、(その1)で記載した大黒天に毘沙門天と弁才天が合体した三面大黒天にあると考えるのなら、比叡山に祀られているものは最澄が彫ったと言われていますから、それは平安時代のこととなります。
では、まず、七福神の「七」という数字から見ていきましょう。
◆「七」
七福神は何故、七柱なのか。
七福神成立の事情について最初に詳しい考察を行った歴史学者、文学博士の喜田貞吉氏(1871-1939)は、次の点を指摘しています。
○「七福」が『仁王護国般若波羅密経』というお経の中に見える、「七難即滅、七福即生」という文言に由来することを指摘
○七人の神様を集めたのは、中国の「竹林の七賢」を下敷きにしていることを示唆 |
「竹林の七賢」とは、3世紀の中国・魏(三国時代)の末期に、酒を飲んだり清談を行なったりして交遊した七人の人物のことで、日本では、室町時代の禅僧たちに好まれ、しばしば絵にも描かれました。
七福神の由来については、この喜田貞吉氏の説が引用されることが多いようです。
また、他にも、数は違いますが、中国に八仙(八福人)なるものがあり、八人の仙人が描かれた絵が信仰の対象とされていたことから、これが七福神の起源となったという説もあります。
さて、一方、この「七」という数字をキリスト教と結びつけるとしたら、それは、もちろん、『ヨハネの黙示録』でしょう。
『ヨハネの黙示録』には、七つの教会、七つの封印、七つのラッパ、七つの平鉢、七つの目と七つの角を持つ小羊、等々、「七」という数字が、これでもか、というくらいに登場します。全登場回数は、五十四回です。
『ヨハネの黙示録』を象徴する数字と言えば、「七」と言って間違いないでしょう。
ちなみに、聖書において「七」は、神が七日間で天地を創造した数字でもあり、「完成、成就、完全」と言った意味を持っています。
なお、ここでは、「七」という数字の共通性を指摘するだけに留めて、先に話を進め、次に、七福神の神々について、個別に見て行きたいと思います。なお、大黒天については、(その1)で記載しましたので割愛します。
◆恵比須
恵比須は、七福神の中で唯一の日本由来の神様で、狩衣(※)、指貫(※)に風折烏帽子を被り、左脇に鯛を抱えて、右手に釣竿を持つ姿が一般的です。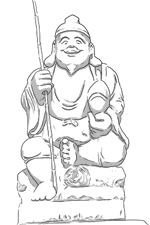
(※)
○狩衣・・・平安時代以降の公家の普段着
○指貫・・・平安時代より男性の略装に用いられた袴の一種
|
恵比須は、唯一の日本の神様とは言え、実際のところ、その出自はよく分かっていません。
一般に唱えられているのは、「蛭子」に由来するという説と、「事代主神」に由来するという説の二説です。
蛭子は、イザナギとイザナミが結婚した時に、最初に生まれた子供ですが、不具の子であった為、葦船に乗せて流されてしまいます。蛭子は「エビス」とも読みます。
一方、事代主神は、大国主神の子で、アマテラスの子孫に国譲りをした後、隠れてしまった神様です。事代主神は、国譲りの際、釣りをしていたことから、海と関係の深い恵比須と同一視されるようになりました。
他にも、恵比須については、釣り竿を抱えた姿から「塩土翁」や、「ホホデミ(山幸彦)」(※釣り針を探して海神の世界へ行った。神武天皇の父。)だとする説もあり、さらに、クジラや海辺に流れ着いた漂流物を「エビス」と呼ぶ地方があり、その地方では、漂流物から思わぬ副収入を得ることがあることから信仰され、恵比須がこの漂着神だとする説もあります。
ちなみに、個人的見解を述べるなら、恵比須の正体は、スサノオと「天照の一人目の巫女」の三男でしょう。
三男は、以下の記事で記載した通り、自説によれば、塩土翁であり、槁根津日子(倭宿禰命)であり、また、八咫烏や宇迦之御魂神でもあります。
そして、槁根津日子は、神武天皇の東征の際、亀に乗って釣りをしながら表れて道案内をしました。この姿は恵比須と重なります。
また、スサノオと、その長男のニギハヤヒ、及び、三男には、キリスト教の三位一体の神が隠されて合祀されており、以下の通り、三男は聖霊に相当します。(※詳細は、上記記事を参照)
○スサノオ ・・・ 天なる父
○長男ニギハヤヒ ・・・ 子
○三男 ・・・ 聖霊
|
恵比須が自説通りなら、キリスト教の三位一体の聖霊に当たり、また、三男の名の一つである宇迦之御魂神について、私は正体を「再臨のキリスト」であるとしていますから、キリスト教と恵比須の関係は、もはや見えてきたと言えるでしょう。(※聖霊と「再臨のキリスト」が同一だという点に、違和感を感じる方もいるかも知れませんが、それについては、記事「5-(29).八咫烏=聖霊」を参照)
(注)
恵比須の正体として、一般的に筆頭にあげられる「蛭子」は、私の解釈では、拙著『古事記に隠された聖書の暗号』に記載した通り、旧約聖書のカインです(その他、イザナギとイザナミはアダムとイブで、蛭子と一緒に生まれた淡島はアベル)。
また、記事「5-(22).天照大御神の一人目の巫女の死因」に記載した通り、イザナギとイザナミの物語には、アダムとイブの話だけでなく、スサノオと「天照の一人目の巫女」の夫婦の物語も反映していますから、蛭子と淡島をその夫婦の子だと捉えることも可能だと思われます。
この点については、まだ考えがまとまっておりませんので、まとまりましたら、別途、記事にします。
|
さらに、恵比須の持ち物について、キリスト教的解釈をしてみましょう。
まず、魚ですが、新約聖書において魚は、神と神の僕たちの網に救い取られるべき人間の魂を表わしています。
『マタイによる福音書』には、次のような記述があります。
『マタイによる福音書』13章47-50節
また、天の御国は、海におろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものです。網がいっぱいになると岸に引きあげ、すわり込んで、良いものは器に入れ、悪いものは捨てるのです。
この世の終わりにもそのようになります。御使いたちが来て、正しい者の中から悪い者をえり分け、火の燃える炉に投げ込みます。彼らはそこで泣いて歯ぎしりをするのです。 |
つまり、魚は人間の魂のたとえに使用され、最後の審判の際、良い魚のみが器に入れられ、悪い魚は地獄の火で焼かれることになるのです。
これは、(その1)で説明した、人を穀物にたとえ、良い実をならせた者とそうでない者を分けるとしているのと全く同じ内容です。
従って、恵比須が抱えている魚は、良い魚であると言えるでしょう。悪い魚であったならば捨てられているはずだからです。
そして、恵比須が持っている釣り竿は、その魚(人間の魂)を釣り上げるための道具であると言えるでしょう。
さらに、魚は、新約聖書において、イエスがパンを1000倍にも増やした話(マタイ14章13-21節、他)にも登場し、また、イエスの命令でペトロが湖に行って釣りをすると、釣れた魚の口から銀貨が一枚見つかり、それで神殿税を支払った話(マタイ17章24-27節)などが記述されています。
このような福音書の記述を踏まえて、魚は初期キリスト教徒たちの間で、キリスト自身のシンボルとなり、また、魚に支えられたり、引っ張られたりする船は、主に導かれる教会の形象であるとされていました。
よって、七福神は船に乗っている姿が一般的ですが、船は教会の象徴であり、日本風に言えば、神社の象徴だと言えるでしょう。
なお、ギリシア語で魚を意味するIXΘYCは、ラテン語に転記するとICHTUSになります。これは「Iesou CHristos Theou Uios Soter」(イエス・キリスト 神の子 救い主)の頭文字となっており、それゆえ、初期の教会では魚がキリストのシンボルとして使用されていました。

「パンと魚の奇蹟の教会」の床モザイク
|
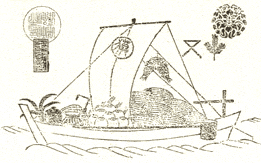
京都の御霊神社が発行した「宝船」の絵 |
| ※4世紀に、イスラエルに建てられた教会で、その名の通り、イエスの奇蹟を記念した教会であり、上記の象徴とは直接の関係はありません。 |
船には、干鯛が吊るされ、碇、鍵、宝珠、米俵などが積まれています |
以上、恵比須は、宇迦之御魂神と同一神であり、やはり、その真の正体は「再臨のキリスト」。
恵比須が持つ魚は、人間の魂の象徴であると同時に、「イエス・キリスト 神の子 救い主」を表わす象徴でもあります。
そして、宇迦之御魂神が持っていた、鎌を釣り竿に、稲を魚に持ち替えたのが恵比須であると言えるでしょう。
上述の通り、稲も魚も人間の魂の象徴であり、鎌と釣り竿は、その、人間の魂を刈り取り、また、釣り上げる道具なのです。
※(その3)へ続く。
◆参考文献等
|

