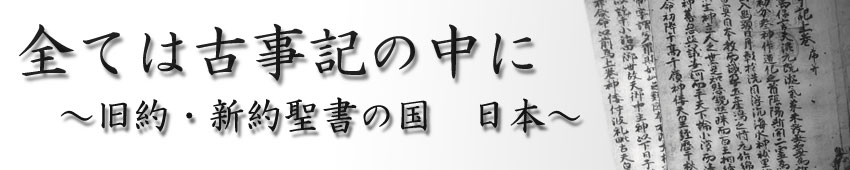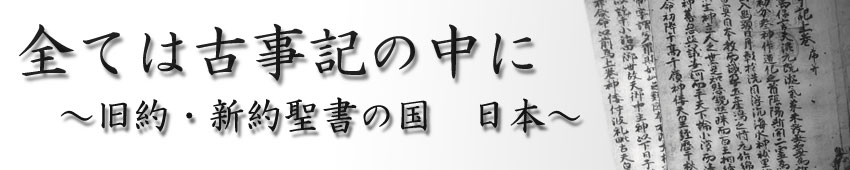| 5-(79).猿田毘古神と塩土老爺(その5) |
※当記事は、(その1)、(その2)、(その3)、(その4)からの続き。
当記事では、塩土老爺と住吉大社の祭神である筒男神との関連を見て行きたいと思います。
5.住吉三神
塩土老爺と住吉三神との関連を見る前に、まず、住吉三神、つまり、底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命について押さえておきたいと思います。
底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命の三神が記紀神話で最初に登場するのは、イザナギの禊祓の時です。
黄泉から帰って来たイザナギは、穢れた国に行ってしまったと水に入って禊ぎをしますが、その時に成った神々の内の三柱が底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命です。
なお、この三神について、『古事記』では「墨江の三前の大神なり」、『日本書紀』(一書(第六)では、「是即ち住吉大神なり」と記載され、大阪の住吉大社で祀られている神であることが説明されています。
そして、次にこの三神が登場するのは神功皇后に対してです。
神功皇后に降りた神は、
「凡そこの国は、汝命の御腹に坐す御子の知らさむ国なり」
|
と告げ、名前を聞かれて、
「こは天照大神の御心ぞ。また底筒之男、中筒之男、上筒之男の三柱の大神ぞ」
|
と答えています(古事記)。
この後、神功皇后は三神の力を借りて三韓征伐を行い、その三神の言葉に従って祀る地を定めますが、『摂津国風土記』逸文には次のように記載されています。
『摂津国風土記』逸文
住吉と称ふ所以は、昔、息長足比売(※)の天皇のみ世、住吉の大神現れ出でまして、天の下を巡り行でまして、住むべき国を覓ぎたまひき。時に沼名椋の長岡の前(前は、いまの神の宮の南の辺、其れ其れの地なり)に到りまして、仍ち謂りたまひしく、「斯は実に住むべき国なり」とのりたまひて、遂に讃め称へて、「真住み吉し、住吉の国」と云りたまひて、仍ち神の社を定めたまひき。いまの俗、略きて、直に須美之叡と称ふ。
※息長足比売・・・神功皇后のこと |
神功皇后は、自分の元に現れた三神を祀る場所を探して現在の住吉大社のある場所にたどりつき、三神が「真住み吉し、住吉の国」と言ったので、そこに社を建てて鎮座したという話です。
6.塩土老爺と住吉三神
続いて、底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命の三神(以下、住吉三神)と塩土老爺と関連を見て行きたいと思いますが、結論から言えば、両神は同一神です。
以下では、その根拠を列挙します。
(1).『住吉大社神代記』
住吉大社に伝わる『住吉大社神代記』には、以下の記述があります(※『住吉大社神代記』は、天平3年(731)に編纂されたとされるが、実際の成立時期については異論あり)。
『住吉大社神代記』
亦、西国見丘あり、東国見丘あり、皆大神(※住吉三神)、天皇に誨え賜いて、塩筒老人に登りて国見せしめ賜いし岳なり。
※『住吉大社』 (住吉大社(編)/学生社/1977) P.79より |
ここでは、住吉三神が塩土老爺に国見をさせたとあり、また、以下の通り、住吉大社自身が書籍『住吉大社』(学生社)の中で、両者が同一神であることを認めています。
『住吉大社』 (住吉大社(編)/学生社/1977) P.110-111
| 塩土老爺とツツノヲノ命 白髪の老翁といえば、『古事記』や『日本書紀』に描かれた塩土老爺を想起する。 〜(中略)〜 鈴木重胤は住吉大神と塩土老翁は全く同一神であろうと説いている(『日本書紀伝』)が、海幸山幸神話そのものが、先述の通り住吉大神の顕現と大いに関係があり、しかも「塩筒」とも記すのであるから、<塩ツツの老翁>は<(底・中・表)ツツの男の命>と語幹をひとしくし、同じ神格、ないし実態を有する神とみてよい。したがって、住吉大神(筒男命)が現形せられた神を塩筒老翁(塩土老翁)として語られているものと考えられる。 |
(2).開口神社
大阪の堺市にある開口神社は、祭神が塩土老爺神他二座で、社伝では、神功皇后の三韓征伐の帰途、この地に塩土老翁神を祀るべしとの勅願により創建されたと伝えています。
また、当社では、塩土老爺神は住吉大社の住吉三神を一つにして神徳を現した神とされています(*2)。
(3).現れた場所
『古事記』、『日本書紀』における両者が顕現した場所を見てみます。
まず、住吉三神ですが、イザナギが禊祓した時に顕現し、その場所は以下のように記載されています。
|
現代語訳 |
| 古事記 |
竺紫の日向の橘の小門の阿波岐原 |
日本書紀
一書(第六) |
筑紫の日向の小戸の橘の檍原 |
日本書紀
一書(第十) |
橘小戸 |
※日向・・・朝日の射す所。
※小戸・・・小さい水門。河の落ち口。
(語義の説明は、『日本書紀(一)』(坂本太郎他(校注)/岩波文庫/1997)P.47注釈一三、一四より)
|
次に、塩土老爺ですが、多くのケースで場所の記載はありません。
ただ、『日本書紀』の一書にのみ、泣いているホホデミ(山幸彦)の元に現れた塩土老爺が、海神の乗り物である八尋鰐がいる場所について以下の通り語っています。
|
現代語訳 |
日本書紀
一書(第四) |
橘の小戸 |
塩土老爺の方でも、住吉三神が生まれた「タチバナのオド」が登場し、関連が伺えます。
以上、塩土老爺と住吉三神は同一神。そして、住吉大社自身が言うように、住吉三神が人の姿を取って現れた姿が塩土老爺と考えて間違いないでしょう。
続いて、(その6)では、猿田毘古神と塩土老爺との関係を見て行きたいと思います。
◆参考文献等
| 書 名 等 |
著 者 |
出 版 社 |
『住吉大社』
|
住吉大社(編) |
学生社 |
|
|
|