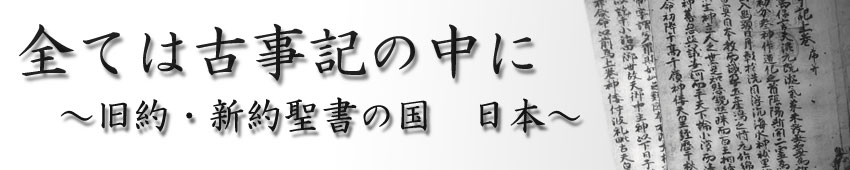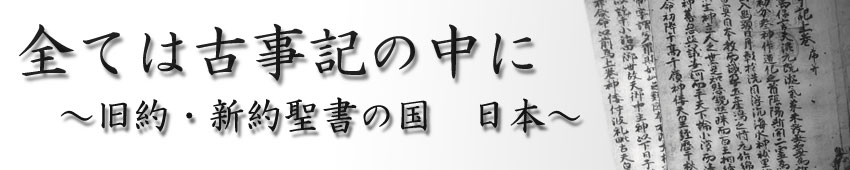| 5-(80).猿田毘古神と塩土老爺(その6) |
※当記事は、(その1)、(その2)、(その3)、(その4)、(その5)からの続き。
当記事では、猿田毘古神と塩土老爺との関係を見て行きたいと思います。
7.猿田毘古神=塩土老爺
猿田毘古神は以下の記事で記載した通り、私は、真の正体をイエス・キリストだと考えており、また、死して上中下と分かれる神が化成しし、キリスト教の三位一体を体現した神だと考えています。
そして、この猿田毘古神と塩土老爺の関係はと言えば、私は同一神であると考えています。
以下にその理由を記載します。
(1).性質
下記の通り、導きの神、海との関わり、農耕神等、両神とも同じ性質を有しています。
【導きの神】
| 猿田毘古神 |
○ニニギが降臨する際、導案内をする為に現れる。 |
| 塩土老爺 |
○兄の釣り針を無くして泣いているホホデミを海神の宮へと導く。
○神武東征のきっかけとなる情報を与える。 |
【海との関わり】
| 猿田毘古神 |
○海で漁をしている時に死亡。 |
| 塩土老爺 |
○ホホデミを海神の宮へと導く。 |
【海中に上中下三つの神】
| 猿田毘古神 |
○海で漁をしている時に死亡し、底どく御魂、つぶたつ御魂」、あわさく御魂という、上中下の三つの魂が生じる。 |
| 塩土老爺 |
○(その5)で記載した通り、「塩土老爺=住吉三神」を前提とすれば、底筒之男命、中筒之男命、上筒之男命と、やはり、海中において上中下と三つの神。 |
【農耕神】
| 猿田毘古神 |
○名前に「田」があり、農耕神としての性質が伺える。 |
| 塩土老爺 |
○「塩土老爺=住吉三神」を前提とすれば、住吉三神は農耕の神としても崇拝されている。 |
【白髭の老人】
| 猿田毘古神 |
○猿田毘古神を祀る神社には白髭神社があるように、白髭の老人として描かれる。 |
| 塩土老爺 |
○名前の通り老人で、白髭の老人として描かれる。 |
このように、猿田毘古神と塩土老爺は、かなりの面でキャラがかぶった神であると言えるでしょう。
(2).九玉神社
鹿児島の九玉神社の由来が書かれた立て札には、祭神が猿田彦大神、また、塩土老爺とあり(*3)、両神が同一神であるとしています。
| (*3)『浦島太郎はどこへ行ったのか』(高橋大輔/新潮社/2005) P.211 |
以上のように、神としての性質が類似し、また、同一神だとしている神社もあることから、両神が同一神であることは間違いないと思います。
さて、(その1)で記載した通り、両神はまるで交代したかの如く登場します。
猿田毘古神はニニギを地上まで送り届けて導き役は終了し、そのまま伊勢へと行ってしまいます。一方、塩土老爺は地上に降りたニニギのもとに現れ、その後、ニニギの子のホホデミ、さらにその孫の神武天皇が東征を開始するまで導き役を果たしています。
単純に考えれば、どうせ、同一神であるなら、全て猿田毘古神で良いように思いますが、何故、わざわざ分けたのでしょうか。
次に、この点について考察したいと思います。
8.猿田毘古神と塩土老爺と「世の光、地の塩」
猿田毘古神と塩土老爺をわざわざ、分けて登場させた理由。私は、その理由が『新約聖書』の中にあると考えます。
『新約聖書』にはイエスの説教が数多く記載されていますが、その中でも有名なものが「山上の垂訓」(「山上の説教」とも言う)と呼ばれるものです。
「山上の垂訓」は、イエスが山の上で弟子と集まってきた群衆に語ったもので、キリスト教の中心的な教義が述べられたものです。そして、その 「山上の垂訓」の中に、「世の光、地の塩」と呼ばれる説教があり、その内容は以下の通りです。
『マタイによる福音書』 5章13-16節 (新共同訳)
「あなたがたは地の塩である。だが、塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや、何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなたがたは世の光である。山の上にある町は、隠れることができない。
また、ともし火をともして升の下に置く者はいない。燭台の上に置く。そうすれば、家の中のもの全てを照らすのである。そのように、あなたがたの光を人々の前に輝かしなさい。人々が、あなたがたの立派な行いを見て、あなたがたの天の父をあがめるようになるためである。」 |
ここでは、自分の中に塩味を持って、役に立ち、かつ、必要とされるものであること、そして、自らが光となって人々を照らす存在であるよう説かれています。
そして、この「世の光、地の塩」と呼ばれる説教の内、「地の塩」を体現しているのが、その名に「塩」を冠している塩土老爺であり、一方、「世の光」を体現しているのが猿田毘古神なのです。
猿田毘古神の名には「光」はありませんが、その登場シーンで以下の通り表現されています。
「邇邇芸命 2.猿田毘古神」 <『古事記』・現代語訳>
さて、日子邇邇芸命が天降りなさろうとするときに、天の八衝にいて、上は高天原を照らし、下は葦原中国を照らしている神がいた。
※標題は『古事記』(倉野憲司校注/岩波文庫/1963)のものを使用 |
「高天原を照らし、下は葦原中国を照らしている神」と、光り輝いて天と地を照らす姿が描かれ、まさに「世の光」として表現されています。
そして、このことが分かれば、何故、両神が交代で現れたのかの説明が出来るようになります。
それぞれが「世の光、地の塩」を象徴しているので、天孫降臨後、舞台が地上に移った後は、「地の塩」を象徴する塩土老爺が導き役を担うことになったのです。
以上、猿田毘古神と塩土老爺は同一神でありながら、それぞれが象徴するものの違いから、日本神話の中で微妙に異なる役割が与えられたのだと思われます。
そして、以下の記事で述べた通り、猿田毘古神の真の正体が三位一体を体現するイエス・キリストであるなら、やはり、塩土老爺の真の正体も同様となります。
また、塩土老爺と同一神である住吉三神は、以下のようにキリスト教の三位一体と対応していることになります。
|
住吉三神 |
キリスト教の三位一体 |
猿田毘古神が死んで
化成した神 |
| 上 |
上筒之男命 |
天なる父(ヤハウェ) |
あわさく御魂 |
| 中 |
中筒之男命 |
聖霊 (天の父と地上の子を仲介する) |
つぶたつ御魂 |
| 下 |
底筒之男命、 |
子(イエス・キリスト) |
底どく御魂 |
さて、このように、猿田毘古神と塩土老爺は同一神で、真の正体はイエス・キリストですが、両神には微妙な属性の違いがあります。
「光」と「塩」との違いのもありますが、その最も大きな違いは、猿田毘古神は既に死んでいるという点です。
猿田毘古神は漁をしている時に死亡しますが、これは、「漁=布教」であり、イエスが布教している最中に磔刑に処されて死亡したことを暗示しています。(※詳細は、記事「5-(67).猿田毘古神=イエス・キリスト(その4)」を参照)
一方、塩土老爺には、そのような物語はありません。
このことは、両神が同じイエス・キリストであっても、別の属性を表すものとして設定されているからであり、その属性は『ヨハネの黙示録』の次の記載に由来しています。
『ヨハネの黙示録』 1章8節 (新共同訳)
| 神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。「わたしはアルファであり、オメガである。」 |
この、「今おられ、かつておられ、やがて来られる方」の内、「今おられ」が塩土老爺、「かつておられ」が猿田毘古神に対応しているのです。
同様のことは、次の記事で、伏見稲荷大社の祭神の解き明かしする際にも説明しましたので、詳細の説明は省きますが、漁、つまり布教の最中に死亡したのは、「かつておられたイエス・キリスト」である猿田毘古神。
そして、「地の塩」に対応する塩土老爺が現在、地上に「今おられるイエス・キリスト」なのです。
以上、参考までに、伏見稲荷大社の祭神と共に、対応を表にまとめておきます。
| 『ヨハネの黙示録』 |
|
伏見稲荷大社 |
備考 |
| 今おられ |
塩土老爺 |
田中大神 |
田の中(=この世)で人々の成長を見守っているイエス・キリスト |
| かつておられ |
猿田毘古神 |
佐田彦大神 |
猿田毘古神で、漁(=布教)の最中に死亡したイエス・キリスト |
| やがて来られる方 |
|
宇迦之御魂大神 |
この世の終末に、良い実を成らせた穀物(=人々)を刈り取る「再臨のキリスト」 |
以上、猿田毘古神と塩土老爺の関連性とその謎について解き明かして来ましたが、続いて(その7)では、住吉大社の配置について見て行きたい思います。
なお、その配置では、上記で説明した「今おられ、かつておられ、やがて来られる方」の対応が重要な意味を持ってきます。
◆参考文献等
| 書 名 等 |
著 者 |
出 版 社 |
『『浦島太郎はどこへ行ったのか』(高橋大輔/新潮社
|
中村陽(監修 |
戎光祥出版 |
|
|
|